【第1章:ビッグバン以前に「何があったのか?」
はじめに:なぜ「ビッグバン以前」が問題になるのか?
「ビッグバン」と聞くと、「宇宙の始まり」として多くの人がイメージする瞬間です。時間、空間、物質、そしてエネルギー──私たちが知る“すべて”がそこから生まれたとされています。
けれど、私たちはどうしてもこう思ってしまいます。
> 「その前はどうなっていたんだ?」
この「前」という発想自体が、実は現代物理学にとって非常にやっかいな問いです。なぜなら、「ビッグバン以前」というのは、そもそも“時間そのものが存在しなかった”かもしれないからです。
それでもなお、理論物理学の世界では「ビッグバン以前」にも何かがあったと考え、その“何か”を解明しようという試みが進んでいます。この記事では、50代の私なりに、できるだけわかりやすく「ビッグバン以前」の仮説とその意味を解説してみます。
—
1. なぜ「無」から宇宙が生まれたとされるのか?
1-1. ハートル=ホーキングの「無境界仮説」
地球儀を思い浮かべてみてください。
地球の「北極点」には「それより北」という場所がありませんよね。でもそこに“壁”があるわけではありません。単に“それ以上先がない”だけです。
ホーキング博士たちは、これと同じように、宇宙にも「始まりに境界がない」とする『無境界仮説』を提案しました。
この仮説では、時間を「虚時間(きょじかん)」という数学的な構造に置き換え、空間のように扱います。こうすると、アインシュタインの一般相対性理論の数式が“ユークリッド空間”として解釈可能になり、特異点(無限大に近づく危険な点)を回避できるのです。
> ■ 図解イメージ:地球儀の北極点のように「それ以上先がない」けれど「壁があるわけではない」──時間にも境界がないとする視点
1-2. ループ量子重力による「バウンス宇宙」
「宇宙は一度収縮して、量子的な効果で再び“跳ね返る”ように膨張した」
そんな大胆な仮説が、ループ量子重力理論から生まれました。
この理論では、空間は連続体ではなく、“スピンネットワーク”と呼ばれる格子状の構造で記述され、面積や体積には「最小単位」が存在します。たとえば次のような式で表されます:
A = 8πγl_p^2 √(j(j+1))
ここで:
γ はイミル係数(ループ量子重力に特有の定数)
l_p はプランク長(時空の最小スケール)
j はスピンの量子数
これによって「特異点」は回避され、ビッグバンは“跳ね返り”現象、つまり「ビッグバウンス」として描かれるようになります。
> ■ 比喩:バウンドするボールのように、宇宙も「一度縮み→弾む」
1-3. ブレーン宇宙論(膜宇宙)
ひょっとしたら、私たちの宇宙は「膜(ブレーン)」かもしれない──。
これは「M理論」と呼ばれる11次元の超弦理論から導かれる仮説です。
この理論では、宇宙は高次元空間に浮かぶ「Dブレーン」として存在し、他のブレーンと“衝突”したことでビッグバンが起きたと考えられています。
> ■ 図解:2枚の膜が近づき、衝突するCG図。衝突時に高エネルギーが発生し、新たな宇宙が膨張し始める。
こうしたブレーン宇宙論は、「始まり」を“次元の運動”として捉えることで、時間の前をも含んだ“より大きな全体像”を描こうとしています。
—
2. 時間の始まりとは?
2-1. 「時間がなかった」とはどういうことか?
時間がなかったとは、一体どういうことでしょうか?
これは「映画のフィルムが静止している状態」をイメージするとわかりやすいです。
フィルムが止まっている限り、私たちは「前のコマ」も「次のコマ」も感じられません。動きがあって初めて、「今」と「次」の違いを感じるのです。
つまり、時間とは「変化があるから存在する」のであって、もし何の変化もなければ、時間も意味を失ってしまいます。
2-2. 時間の“出現”
最新の理論では、「時間」は最初からあったのではなく、場(エネルギー場)や重力によって“現れた”のではないかと考えられています。
時間の変化は、たとえば「宇宙のスケール因子 a(t)」によって記述されます:
ds² = -dt² + a(t)² dx²
ここで a(t) が非常に小さい、つまり宇宙が極端に圧縮されていた時には、時間の進み方も“消えかける”ような挙動を示します。
—
3. 宇宙起源に関する仮説の比較
3-1. 量子揺らぎ仮説
「完全な無」は存在しない──これが量子力学の基本的な見方です。
どんなにエネルギーが低い“真空”でも、微細な「ゆらぎ(揺れ)」は常に起きています。
この“ゆらぎ”が、ある瞬間、突発的にエネルギーを持ち、宇宙を形成したというのがこの仮説です。
> ■ 比喩:沸騰直前のお湯が「ボコッ」と泡を出すように、エネルギーゆらぎが宇宙を“はじけさせた”
3-2. 真空の相転移仮説
「相転移」とは、たとえば水が氷に変わるときのような“状態の変化”を意味します。
宇宙も、はじめは“偽の真空”と呼ばれる高エネルギー状態にあり、そこからトンネル効果で一気に“本当の真空”に変わったという説です。
[偽の真空] → トンネル効果 → [安定した真空]
> ■ 比喩:過冷却水が突然、氷に変わるときのような「瞬間的変化」
3-3. マルチバース仮説(多宇宙論)
もし宇宙が1つだけではなく、「無数の宇宙(バブル)」が生成されていたとしたら?
「マルチバース仮説」は、インフレーション理論と量子論の組み合わせから生まれた、“泡宇宙”の概念です。
私たちの宇宙もその中の1つであり、他の宇宙では物理法則や定数すら異なる可能性があります。
> ■ 比喩:泡風呂の中の1つ1つの泡が、それぞれ異なる宇宙──私たちはその一つに過ぎない
—
まとめ
「ビッグバン以前に何があったのか?」──これは50代になってようやく、自分なりにじっくり向き合いたくなった問いでもあります。
時間という概念も、空間も、私たちの直感とはまるで違うかたちで“始まり”を迎えた可能性がある。
それを突き詰めていくと、「始まり」とは自然現象そのものであり、私たち人間の人生の時間軸とも、どこか重なって見えてくるのです。
物理学は、ただ難しい理論を追うだけでなく、「自分はどこから来て、どこへ行くのか」を考える手がかりにもなる──。
そんな視点で、次回は「宇宙がどうやって“形”を持ち始めたのか」に踏み込んでいきます。
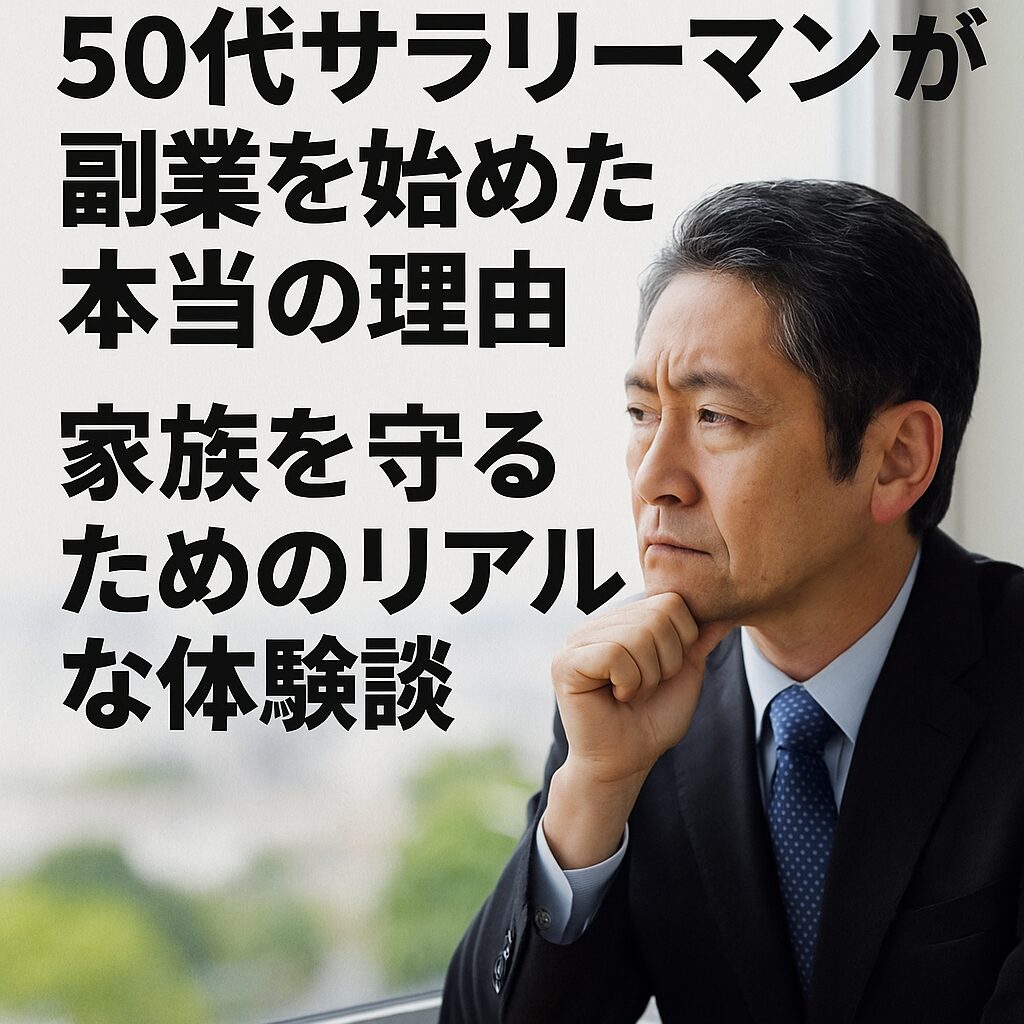

コメント